イノベーションのリスクをとらないということは、イノベーションをしない(新しいことをしない)ということに等しい。スマート(賢い)リスクをとる風土を作る
第2回 賢いリスクをとる(2013.04.23)
プロジェクトマネジメントオフィス 好川 哲人
◆スマートリスクマネジメント
戦略ノート第2回。実質的な初回なので、何について書こうかと思って少し迷ったが、スマートリスクという話題を選んだ。スマートという言葉がはやり言葉になっているが、リスクにもスマートという言葉が使われるようになってきた。「スマートリスク」である。スマートリスクって初めて聞くという人も多いと思うが、スマート=賢いで、「賢いリスク」という意味。リスクが賢いわけではなく、リスクをとることが賢い、つまり、妥当であるという意味だ。
システム開発のように失敗をすることが許されないオペレーション型のプロジェクトの場合、リスクはできるだけ回避したい(とりたくない)。だから、技術にしろ、工法にしろ、プロセスにしろ、できるだけ新しいことをしたくない。これがリスクマネジメントの本分であり、この体質がしみ込んでいるのがイノベーションができない一つの理由だ。
イノベーションのリスクは取ってナンボだ。リスクをとらないということは、イノベーションをしない(新しいことをしない)ということに等しい。取ったリスクをなんとか潜り抜けながらプロジェクトを進めていくことがリスクマネジメントの本分である。
PM養成マガジンの戦略ノートにスマートリスクのマネジメントについて書いたことがあるので、こちらも参考にしてほしい。
【戦略ノート278】スマート・リスクマネジメント
◆消極的にリスクをとると失敗する
スマートリスクの問題はリスクマネジメントの問題と同じくらい、リスクをとる風土を作ることが重要である。こういうことを考えてみてほしい。今回のイノベーションにはどうしてもあるリスクが生じる。避けることはイノベーションをやめることである。そこで、いやいやリスクをとるか、積極的にリスクをとるかはだいぶ違う。いやいやリスクをとったら必ず失敗する。リスクに立ち向かう力がないからだ。よくスポーツとかで勝てる相手ではないと分かっていて、何もせずに終わってしまうことがある。これと同じだ。何かしないと勝てない。勝てる相手ではなくても勝てることもあるかもしれない。イノベーションのリスクとはそういうものだ。
積極的にリスクをとっていく姿勢が重要なのだ。
◆積極的にリスクをとるには
そこで、リスクマネジメント以前の問題として立ちはだかるのが、リスクをとるという問題なのだ(もちろん、これはリスクマネジメントとしてはリスク戦略の決定という位置づけになるわけだが)。ちょっと話が大きくなるが、イノベーティブな会社とそうでない会社の違いを一つだけ挙げるとすれば、リスクをとっているかどうかを上げたい。もう少し正確にいえば、単にリスクをとることだけではなく、リスクをとったことを褒めてもらえる会社である。
どうすれば積極的にリスクをとる会社になれるのか。これがイノベーションを成功させるのに決定的な要因である。
◆スマートリスクを取るために必要な風土
スマートリスクをとる背景には、・新しいアイデアを考える
・現状に疑問を持つ
・挑戦する
・試してみる
といったことを奨励する風土がある。そして、奨励するだけではなく、スマートリスクをとることに喜んで報酬を払う価値感がある。
スマートリスクをとる風土を作るには何をすればいいのだろうか?この問いは、イノベーティブな組織にするには何をすればよいかとイコールかもしれない。
スマートリスクの話をすると、根本的な勘違いをされることがある。それはスマートリスクもリスクと同じように識別するものだと思ってしまうことだ。リスクが賢いものかどうかは、一般的に判断するものではない。
◆スマートリスクの定義をはっきりさせる
あくまでも組織が自らの感覚で決めるものだ。言い換えると、何がスマートリスクで、何がスマートでないかは、定義する必要があるわけだ。ここが風土づくりのスタートだ。ここを経営層に勝手に決められるようなことがあっては、安心してリスクは取れない。スマートリスクであることを定義しようとすると指標が必要だ。その指標であるが、たとえば、
・イノベーションにかかる時間
・イノベーションの財務的影響
・イノベーションに必要なリソース
・プロトタイプのクリアすべき条件
といったことが指標になる。これらの指標を用いて、リスクとして取るべき範囲を定義するとスマートリスクとはどのようなものかがはっきりする。ただし、定量的な基準を設定すると一人歩きするし、スマートかどうかはそのプロジェクトのリーダーやメンバーの能力や認識にも依存するので、ある程度の曖昧さを残しておく方がよい。この曖昧さもスマートリスクだということだ。
◆成功の定義をはっきりさせる
二番目に重要なことは成功の定義だ。通常のプロジェクトでは成功の定義を定め、最終的にはプロジェクトの成功率を決定し、それを事業や経営の目標の一つとして使う。しかし、イノベーションのプロジェクトでは、成功率を上げたいために成功の定義を使いたいわけではない。あくまでも失敗率の許容範囲を明確にし、(スマート)リスクのコントロールするために成功の定義を使う。したがって、通常のプロジェクトのように厳密な定義である必要はない。
◆スマートリスクをとった社員が称えられる
三番目はスマートリスクをとった社員が称えられることだ。これがないと口でいくらリスクをとれといっても社員は信じない。称える方法は最終的には評価だが、その前に全員の前で賞賛されるといったパフォーマンスが大切だ。失敗した、成功したではなく、リスクをとったという行動をたたえること。特にうまく行った場合には、称えてもあまり意味がない。では、失敗しても褒めるのがいいかというとそう単純でもない。失敗を恐れないという空気は生まれても、緊張感がなくなると困る。
従って、リスクを取ることの勇気をたたえることが重要なのだ。
◆関連セミナー
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆イノベーション力を身につける ◆(7PDU's)
日時・場所:【Zoom】2026年 05月 08日(金)9:30-17:30(9:20入室可)
※Zoomによるオンライン開催です
※ハーフセミナーは、事前学習3時間あります
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木道代(プロジェクトマネジメントオフィス、PMP、PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/innov_skill2.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「イノベーションを生み出す力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.イノベーション力の3つの軸
2.アイデアを生み出すマインド
(演習)テーマを決める
3.アイデアを生み出す思考法
(演習)アイデアを生み出す
4.アイデアを実現する行動
(演習)アイデアの実現方法を考える
5.まとめ〜アイデアを解放する
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆質問力はこちら
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆問いから始まるイノベーション ◆(7PDU's)
日時・場所:【Zoom】2026年 06月 11日(木)9:30-17:30(9:20入室可)
※Zoomによるオンライン開催です
※ハーフセミナーは、事前学習3時間あります
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木道代(プロジェクトマネジメントオフィス、PMP、PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/inquir2.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「イノベーションを生み出す質問力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.質問がイノベーションを生む
2.誰に質問するのか
3.質問の構造と技術
(演習)パワークエスチョンを作る
4.イノベーションを生む質問
(演習)挑発的な質問、破壊的な質問を作る
5.質問力を養うには
6.イノベーションの場を作る
7.質問ストーミング(ワークショップ)
(演習)質問ストーミングで質問を作る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者紹介
好川哲人、MBA、技術士
株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表、PMstyleプロデューサー
15年以上に渡り、技術経営のコンサルタントとして活躍。プロジェクトマネジメントを中心にした幅広いコンサルティングを得意とし、多くの、新規事業開発、研究開発、商品開発、システムインテグレーションなどのプロジェクトを成功に導く。
1万人以上が購読するプロジェクトマネジャー向けのメールマガジン「PM養成マガジン(無料版)」、「PM養成マガジンプロフェッショナル(有料版)」や「コンセプチュアル・マネジメント(無料」、書籍出版、雑誌記事などで積極的に情報発信をし、プロジェクトマネジメント業界にも強い影響を与え続けている。
メルマガ紹介
本連載は、コンセプチュアル・マネジメント購読にて、最新の記事を読むことができます。
コンサルティングメニュー紹介
PMOコンサルティング、PMOアウトソーシングサービス、人材マネジメントサービスなど、御社に最適のコンサルティングをご提案させていただきます。まずは、お問合せください。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

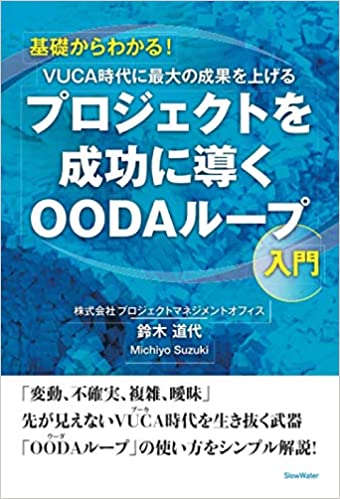
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/06/17,19☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/6/11☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/4/1☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/12☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/18☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/27,29☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/5/28☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索