イノベーティブなリーダーの思考様式として、まず前提を疑うことが重要である。ルールを変える、謙虚であることで、前提を崩すことができる。前提を捨て去るとたちまち、新しいアイデアが生まれる
第8話 イノベーティブリーダーの思考法(1)(2013.06.11)
プロジェクトマネジメントオフィス 好川 哲人
◆イノベーティブリーダーの思考法
久しぶりのイノベーション・リーダーシップ。今回から少し、イノベーティブ・リーダーの思考法について考えてみたい。思考法という場合、2つの意味合いがある。一つは文字通り「思考法」で、頭の使い方だ。イノベーティブ・リーダーの代表的な思考法というと、ラテラル・シンキング(水平思考)と呼ばれるものだが、それ以外にもクリティカルシンキングやコンセプチュアルシンキングなども有効である。実は、これらの思考法の体系というのはMECEにはなっておらず、たとえば、前提を疑うという思考様式は3つのいずれでも言われている。そこで、ここでは、これらの思考法の枠を設けずに、思考の原則について述べていく。
もう一つの思考法の意味合いは、リーダーシップの意味合いで、イノベーションを実行する、あるいはイノベーションを推進するリーダーとしてどのように考えるかである。こちらの思考法は、マネジメントの議論であるのでイノベーションマネジメントの連載で取り上げていくこととし、ここでは取り上げない。
◆イノベーティブリーダーの思考様式
さて、イノベーティブリーダーの思考様式としてよく見かけるものを思いつくままに挙げてみると
・前提を疑う
・ルールを変える
・視点を変える
・質問をする
・組み合わせを変える
・失敗を歓迎する
・試して評価する
・アイデアを改良する
・アイデアを増やす
・抽象と具象を考える
といったものがある。
これらについて、説明をしていく予定である(増えたり、減ったするかもしれない)。
◆前提を疑う
さて、まず、前提。前提を疑うという思考様式はイノベーティブ・リーダーの思考法としてはもっとも重要なものかもしれない。イノベーションは常識や先入観に束縛されているからだ。これらの前提を捨て去るとたちまち、新しいアイデアが生まれることは珍しくない。では前提を見つけるには、前提の潜んでいる場所を知ることである。これは、プロジェクトマネジメントで計画の際に前提を見つけるにも役立つので、ぜひ知っておいてほしい。
◆概念に潜む前提
まず、最初は定義そのものに前提が含まれている場合がある。たとえば、少し前までは日本ではイノベーションの議論は技術マネジメントの中で行われていた。その理由はイノベーションという概念の定義には技術を革新することであるという前提があったからだ。イノベーションという言葉を初めて使ったのは、オーストリアの経済学者シュンペーターで、著書「経済発展の理論」の中で、経済発展は、人口増加や気候変動などの外的な要因よりも、イノベーションのような内的な要因が主要な役割を果たすと指摘した。
そして、イノベーションとは、新しいものを生産する、あるいは既存のものを新しい方法で生産することであり、生産とはものや力を結合することと述べており、イノベーションの例として、
(1)創造的活動による新製品開発
(2)新生産方法の導入
(3)新マーケットの開拓
(4)新たな資源(の供給源)の獲得
(5)組織の改革
などを挙げている。
この概念を日本に持ち込むときに、なぜか「技術革新」と命名した。これ以来、イノベーションは技術の革新であるという前提ができてしまった。日本人がこの前提を疑うきっかけになったのは、おそらくアップルの躍進であり、前提を変えて生まれてきた商品としてWiiが有名である。
◆経験に潜む前提
二つ目は、経験である。経験が前提になる。たとえば、ソフトウエアの開発においては、システムの要件を如何に早い時期に確定するかが成否にカギを握っていると多くのエンジニアが考えていた。
そこで、できるだけ早く要件を確定するための方法をいろいろと工夫する中で、その前提を覆すイノベーティブな方法が生まれた。
アジャイル開発である。
◆常識に潜む前提
三つ目は常識である。身近な例で、常識に含まれる前提を変えたサービスですごいと思うのが、鉄道のプリペイドカードである。
かつて、電車に乗るには、行き先や行き方を決めて切符を購入し、改札を通っていた。人は行き先や行き方を決めて電車に乗るという常識があった。プリペイドカードはこの常識を変えた。取り敢えず乗ってしまい、そのあとで行き先を変えることもできるし、行き方を変えることもできるようにした。これは結構大きなイノベーションである。
◆前提を崩すには
このように前提はいろいろな場所に含まれているわけだが、では、どうすれば崩せるのだろうか?上の事例を考えてみるといくつか原則があることが分かる。まず、一つはルールを変えることだ。アジャイルやプリペイドカードの例はそれである。
二つ目は謙虚であることだ。有利な立場にある企業ほど、前提や先入観にとらわれる傾向がある。一種の成功体験である。したがって、不都合が起こったときにルールや常識を変えようとすることはあっても、自らルールを変えることはない。こういう発想を防ぐには謙虚さを忘れないことだ。
◆関連セミナー
クリティカルシンキングのセミナーを開催します。ご参加お待ちしています。━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える ◆7PDU's
日時・場所:【Zoom】2026年 04月 15日(水)9:30-17:30(9:20入室可)
【Zoomハーフ】2026年 06月 24日(水)13:00-17:00+3時間
【Zoomナイト】2026年 03月 11日(水)13日(金) 19:00-21:00+3時間
※Zoomによるオンライン開催です
※ナイトセミナーは、2日間です
※ハーフセミナー、ナイトセミナーは、事前学習が3時間あります。
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木 道代(株式会社プロジェクトマネジメントオフィス,PMP,PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/critical.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「クリティカルシンキング」「プロジェクトマネジャーのためのシステム思考」
「クリティカルシンキングはプロジェクトマネジメントに必要」
「クリティカルシンキングで影響力の武器を使う」
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【カリキュラム】
1.クリティカルに考えるとは
2.ロジカルシンキング
3.何を疑うのか(合理性)
4.何を疑うのか(内省)
5.クリティカルシンキングの4ステップ
6.具体的状況におけるクリティカルシンキング演習
7.クリティカルシンキング総合演習
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践 ◆7PDU's
日時・場所:【Zoom】2026年 03月 11日(水)9:30-17:30(9:20入室可)
【Zoomハーフ】2026年 04月 08日(水)13:00-17:00+3時間
【Zoomナイト】2026年 06月 10日(水)12日(金) 19:00-21:00+3時間
※Zoomによるオンライン開催です
※ナイトセミナーは、2日間です
※ハーフセミナー、ナイトセミナーは、事前学習が3時間あります。
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木 道代(株式会社プロジェクトマネジメントオフィス,PMP,PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/critical_practice.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「クリティカルシンキング」「プロジェクトマネジャーのためのシステム思考」
「クリティカルシンキングはプロジェクトマネジメントに必要」
「クリティカルシンキングで影響力の武器を使う」
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【カリキュラム】
1.クリティカルシンキングトレーニング
【講義】仕事の本質を考え、関係者として、評価する
【エクスサイズ】現状を疑う
【エクスサイズ】問題を疑う
【エクスサイズ】視点を変え、別の可能性を追求する
2.クリティカルシンキング応用(1)〜要求分析
【講義】本質要求を探す
【エクスサイズ】顧客の現状認識を疑う
【エクスサイズ】顧客の要求を疑う
【エクスサイズ】顧客の要求の本質を追求する
3.クリティカルシンキング応用(2)〜リスクマネジメント
【講義】クリティカルシンキングとリスクマネジメント
【エクスサイズ】プロジェクト計画を疑う
【エクスサイズ】プロジェクト目標を疑う
【プロジェクト】クリティカルシンキングでプロジェクト計画を見直す
4.クリティカルシンキング応用(3)〜ステークホルダーマネジメント
【講義】ステークホルダーを多面的に分析する
【エクスサイズ】リスクからステークホルダーを特定する
【エクスサイズ】ステークホルダーの影響力を疑う
【エクスサイズ】視点を変え、ステークホルダーの意識を変える
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
著者紹介
好川哲人、MBA、技術士
株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表、PMstyleプロデューサー
15年以上に渡り、技術経営のコンサルタントとして活躍。プロジェクトマネジメントを中心にした幅広いコンサルティングを得意とし、多くの、新規事業開発、研究開発、商品開発、システムインテグレーションなどのプロジェクトを成功に導く。
1万人以上が購読するプロジェクトマネジャー向けのメールマガジン「PM養成マガジン(無料版)」、「PM養成マガジンプロフェッショナル(有料版)」や「コンセプチュアル・マネジメント(無料」、書籍出版、雑誌記事などで積極的に情報発信をし、プロジェクトマネジメント業界にも強い影響を与え続けている。
メルマガ紹介
本連載は、コンセプチュアル・マネジメント購読にて、最新の記事を読むことができます。
コンサルティングメニュー紹介
PMOコンサルティング、PMOアウトソーシングサービス、人材マネジメントサービスなど、御社に最適のコンサルティングをご提案させていただきます。まずは、お問合せください。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

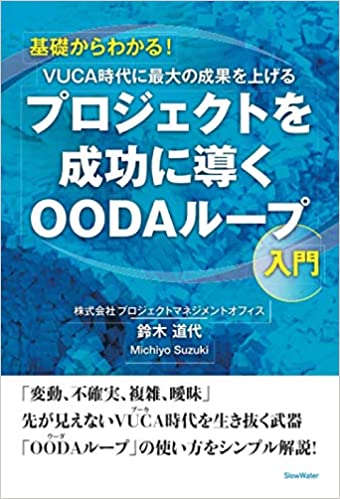
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/02/25,27☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/2/19☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/2/25☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/16☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/2/18☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/2/18,20☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/2/20☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/2/21☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索