ダイバーシティーを競争に活かしていく活動が必要であり、それがダイバーシティーマネジメントである。ダイバーシティーマネジメントが行われない一つの原因として、具体的・形式的なレベルだけで意見を戦わせていることがある
第4回 本質に着目したダイバーシティー・マネジメントのイメージ(2018.09.21)
プロジェクトマネジメントオフィス 好川 哲人
◆はじめに
今回で4回目になります。第1回で概論をした後、第2回はコンセプチュアル・マネジメント的なリソース活用の方法、第3回ではビジョンを重視したイノベーションの起こし方について考えてみました。
今回はダイバーシティーマネジメントの議論をしたいと思います。
ダイバーシティーは10年くらい前から日本でも経営のキーワードの一つだと考えられるようになっていますが、いまだに、その地位は確立したとは言えないのが現状です。その原因の一つは、適切なマネジメントが行われていないことだと思われます。
◆多様性は競争の邪魔になるという前提
ダイバーシティーが必要だと考えられている理由は幅広いのですが、「多様性を認める」ことに置かれているケースが多いようです。つまり、従業員が自由に自分の意見を述べ、組織としてうまく調整されていくことを目的にしているケースが多いのです。例えば、日本人男性とは発想の異なる女性や外国人を活用するというのはその典型だといえるでしょう。
一方で、こういう目的でダイバーシティーを考えていると、必ずと言ってよいくらい「そうありたいが現実は回らない」という意見が出てきます。そして、従来通りの考え方、やり方から脱却しないというパターンが目立ちます。
つまり、「多様性は競争の邪魔になる」という前提があるのです。もう少しいえば、組織がうまく運営できればビジネスもうまくいくと考えられています。これは正しいのでしょうか。
組織をうまく運営することはビジネスが成功することの必要条件かもしれませんが、十分条件ではありません。
そう考えると、この前提は正しいとは言えず、外す必要がありますが、そのためには、多様性を競争優位の源泉として活かすという発想が必要です。そのためにのプログラム、文化や制度を作り上げていくことが必要です。簡単にいえばダイバーシティーを競争に活かしていく活動が必要で、これがダイバーシティーマネジメントなのです。
◆ダイバーシティーマネジメントが行われない理由
では、どうしてダイバーシティーマネジメントが行われていないのでしょうか。そもそも、マネジメントが行われていないという問題もありますが、ここではこの問題については考えないことにします。
ダイバーシティーマネジメントが行われない一つの原因として、具体的・形式的なレベルだけで意見を戦わせていることがあげられます。
このようなスタンスですと、異なる価値観を持った人の間で意見が統合されることはまずありません。どちらかの意見が採用され、どちらかは捨てられます。あるいは、そのまま足して2で割るようなまとめ方がされることもあります。
例えば、ある製品群を成長させるに当たって、イノベーションを推進するか、より一層のコストダウンを図るかで対立があったとします。すると、具体的なレベルでいくら議論しても、どちらのか意見を採用するのかという範囲を超えることはありません。せいぜい、コストダウンに直結するような技術イノベーションを行うといった短絡的な考えが出てくるくらいでしょう。
◆本質を考えて統合を図る
ここで考えるべきは、イノベーションを行うことの本質は何か、コストダウンを行うことの本質は何かです。そして本質レベルで意見を交えると、具体的なレベルよりはるかに統合しやすくなります。
例えば、
イノベーションの本質 → 顧客に新しい機能を提供すること
コストダウンの本質 → 顧客に新しい用途を提供すること
だったとします。すると、これらは顧客に新しい価値を提供することに統合・集約できます。ここがうまく整理できれば、この統合された本質のもとで具体的な製品やサービスを考えることはそんなに困難なことではありません。
このような展開を担当者同士で行うことは難しく、やはりそのように導いていくマネジメントが不可欠です。
(続く)
◆関連するセミナーを開催します
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆コンセプチュアルな組織を創るマネジメント ◆(7PDU's)
日時・場所:【Zoom】2026年 02月 18日(水)9:30-17:30(9:20入室可)
※Zoomによるオンライン開催です
※ハーフセミナーは、事前学習3時間あります
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木道代(プロジェクトマネジメントオフィス、PMP、PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/conceptual_management.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「コンセプチュアルスキルとは(前半)」「コンセプチュアルスキルで行動が変わる」
「イノベーションを生み出す力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.コンセプチュアルではない組織の問題点
・個人レベルの問題点
・チームレベルの問題点
・組織レベルの問題点
2.コンセプチュアルなマネジメントのポイント
2.1 質問型の組織を創る
2.2 コンセプチュアルな組織活動のプラニング
2.3 ステークホルダーへのコンセプチュアルな対応
2.4 コンセプチュアルな人材育成
2.5 コンセプチュアルな組織文化の構築
3.コンセプチュアルなマネジメントの目標
4.コンセプチュアルマネジメントでコンセプチュアルな組織を創る仕組みワークショップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者紹介
好川哲人、MBA、技術士
株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表、PMstyleプロデューサー
15年以上に渡り、技術経営のコンサルタントとして活躍。プロジェクトマネジメントを中心にした幅広いコンサルティングを得意とし、多くの、新規事業開発、研究開発、商品開発、システムインテグレーションなどのプロジェクトを成功に導く。
1万人以上が購読するプロジェクトマネジャー向けのメールマガジン「PM養成マガジン(無料版)」、「PM養成マガジンプロフェッショナル(有料版)」や「コンセプチュアル・マネジメント(無料」、書籍出版、雑誌記事などで積極的に情報発信をし、プロジェクトマネジメント業界にも強い影響を与え続けている。
メルマガ紹介
本連載は、「コンセプチュアル・マネジメント」購読にて、最新記事を読むことができます。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

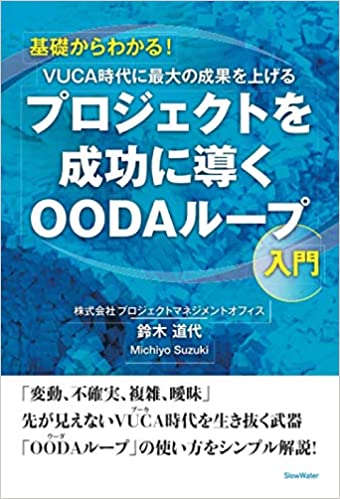
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/02/25,27☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/2/19☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/2/25☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/16☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/2/18☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/2/18,20☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/2/20☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/2/21☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索