現実をどのような問題として捉えるかが「問いを立てる」ことであり、問題解決より、大切。イノベーションにはキラークエスチョンがある
第79話:質問について考える(2014/02/05)
プロジェクトマネジメントオフィス 好川 哲人
◆問題解決より、問題のとらえ方が大切な時代
今、いろいろな意味で重要だと考えられているのが「問い」です。いろいろな背景がありますが、我々が直面する問題が複雑化するにつれて、問題解決自体より、どのような問題として捉えるかのほうが重要になってきました。たとえば、女性活用が求められる中で、長時間労働がネックになって、子供を持つ女性が職場で男性と同じような条件で働くのが難しいという現実があります。この現実においては、問題はいろいろと考えられます。たとえば
・生産性が悪い
・マネジメントができていない
・育児の負担が女性に偏っている
・育児の支援の環境が不十分である
などです。これらはいずれも問題になりうるわけで、現実をどのような問題として捉えるかのセンスが求められます。
そして、現実をどのような問題として捉えるかが「問いを立てる」ことに他なりません。ということで問いを立てることが重要だと考えられるわけです。
どのような分野でも問いを立てることは重要なのですが、中でも重要性が認識されるようになってきたのが「イノベーション」です。イノベーションはもともと問題や課題によって成果が決まる分野だからです。
◆イノベーションにおける質問の重要性
イノベーションにおける問いの重要性はさまざまな識者が指摘しています。それを紹介する前に言葉のニュアンスを説明しておきます。この記事の中では、「問い」と言う言葉と「質問」という言葉をある程度、意図的に使い分けています。問いとは抽象度の高いものであり、質問とは具体的なものです。もちろん、厳密に分けられるものではありませんが、一応、ニュアンスはそんな感じです。この問題は後でもう一度触れますが、とりあえずそんなニュアンスを感じて読んで戴ければと思います。
さて、イノベーションの話に戻ります。イノベーションに関する問いかけでもっとも分かりやすいのは、「前提や常識は正しいのか」という質問ですが、もっと体系的に捉えている人もいます。
まずは「イノベーターのジレンマ」でおなじみのクレイトン・クリステンセン教授です。クリステンセン教授は、「イノベーターのジレンマ」シリーズの最後になる「イノベーターのDNA」の中でイノベーターに求められるスキルを整理して、「関連付ける力」、「質問力」、「観察力」、「ネットワーク力」、「実験力」の5つの発見力に区分しました。
◆スティーブ・ジョブズの問い
そして、質問が創造的な洞察を生み出す可能性があり、質問を変えれば世界を変えることができると断言しています。その例として、そこで例として取り上げられているのが、スティーブ・ジョブズがアップルに復帰した時に問いかけたとされる有名な質問「金が問題でなければ、何をする」
です。当時、アップルの製品は、経営的な制約でジョブスがいた当時とは比較にならないくらい縮退していました。だから、一度はアップルを出たジョブズが再び復帰できたともいえますが、いずれにしても、経営的制約という製品開発にとってはもっとも大きな前提を変える問いかけをしたわけです。
そして、この問いに応えるようにアップルの快進撃が始まり、iMac、iPodやiTune、iPhone、iPadと画期的な製品を続々と生み出していきました。
ここにきて、ジョブズの質問は忘れ去られているように見えますが、このジョブズの質問が生きていれば、アップルは今後もイノベーティブな企業であり続けるのではないでしょうか?
多くの人が経験していると思いますが、具体的な質問は改善の視点を生み出します。抽象的な質問(問い)はイノベーションの「視座」を生み出します。イノベーションを生み出すために必要なのは視点より、視座です。言い換えるとイノベーションを興すには抽象的な質問が必要であるともいえます。
◆キラークエスション
もう一つ体系的な質問を挙げます。ニューヨークでイノベーション関連の調査や教育を手掛ける会社を経営するリサ・ボデルは、イノベーションにはキラークエスチョンがあると指摘しています。キラークエスチョンとは未来に目を向けた挑発的とも思えるような質問のことです。
たとえば、「今年の利益率はいくらか」といった質問では未来に目が向けられることはありません。ところが、「来年とりくみたいことを3つ挙げるとすればなんですか」と質問すると、嫌でも未来に目が向きます。
キラークエスチョンとはこのような質問のことです。ちなみに、リサ・ボデルが気に入っているキラークエスチョンは
結局われわれは何のビジネスをしているのだろうか
という質問だそうです。
この質問は企業が常に自分たちの価値を見直し、イノベーションを生み出していくのに、非常に効果的な質問だといえます。
◆どのような場で質問するか
このようにイノベーションにとって質問は極めて重要な意味を持っています。では、どのような場で、質問をすればいいのでしょうか?これは立場やマネジメントのスタイルによって変わると思われます。たとえば、あなたがマネジャーであれば、思いつくがままに次々と質問を発し、メンバーを刺激し、対話するという方法があります。ジョブズのやり方はこのスタイルに近かったようです。
対話するだけではなく、グループやチームで議論したいのであればグループセッションを行う方法もあります。フューチャーセッションとか、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)セッションなどがイノベーションのきっかけになりやすいと言われていますが、ワールドカフェのような混ぜる手法やもっと古典的なブレーンストーミングなども有効です。
ちなみに、質問だけで議論をする方法として「質問会議」が有名ですが、ブレーンストーミングを質問を中心に進めていく質問ストーミングといった方法もあります。
また、質問は必ずしも対話やグループセッションの中で発せられるだけではありません。自問をすることも非常に有効な質問の方法だといえます。自問を考える場合には、クリティカルシンキングと呼ばれる思考法とセットにして身につけると効果的です。
◆質問だけでは十分条件ではない
最後にイノベーションにおける質問について重要な点を述べておきます。クリステンセン教授が指摘しているように、質問はイノベーションにとって必要条件であっても十分条件ではないということです。考えてみると当たり前のことですが、わざわざ指摘していることからも分かるように意外とはまりやすい落とし穴です。
たとえば、フューチャーセッションはイノベーションを起こす効果的な手段です。これは実績的に考えても間違いありません。しかし、フューチャーセッションだけでは机上の議論にすぎません。たとえば、そこに、エスノグラフィー(観察)が組み合わさって質問の質も変わるし、よりイノベーションが起こりやすくなります。質問に何を組み合わせるかで質問の威力が決まるといっても過言ではないことを意識しておく必要があります。
◆参考資料
[1]クレイトン・クリステンセン、ジェフリー・ダイアー、ハル・グレガーセン(櫻井 祐子訳)「イノベーションのDNA 破壊的イノベータの5つのスキル」、翔泳社(2012)
[2]リサ・ボデル(穂坂 かほり訳)「会社をつぶせ―ゾンビ組織を考える組織に変えるイノベーション革命」、マグロウヒル・エディケーション(2013)
◆関連セミナー
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆コンセプチュアルな組織を創るマネジメント ◆(7PDU's)
日時・場所:【Zoom】2026年 05月 12日(火)9:30-17:30(9:20入室可)
※Zoomによるオンライン開催です
※ハーフセミナーは、事前学習3時間あります
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木道代(プロジェクトマネジメントオフィス、PMP、PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/conceptual_management.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「コンセプチュアルスキルとは(前半)」「コンセプチュアルスキルで行動が変わる」
「イノベーションを生み出す力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.コンセプチュアルではない組織の問題点
・個人レベルの問題点
・チームレベルの問題点
・組織レベルの問題点
2.コンセプチュアルなマネジメントのポイント
2.1 質問型の組織を創る
2.2 コンセプチュアルな組織活動のプラニング
2.3 ステークホルダーへのコンセプチュアルな対応
2.4 コンセプチュアルな人材育成
2.5 コンセプチュアルな組織文化の構築
3.コンセプチュアルなマネジメントの目標
4.コンセプチュアルマネジメントでコンセプチュアルな組織を創る仕組みワークショップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者紹介
好川哲人、MBA、技術士
株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表、PMstyleプロデューサー
15年以上に渡り、技術経営のコンサルタントとして活躍。プロジェクトマネジメントを中心にした幅広いコンサルティングを得意とし、多くの、新規事業開発、研究開発、商品開発、システムインテグレーションなどのプロジェクトを成功に導く。
1万人以上が購読するプロジェクトマネジャー向けのメールマガジン「PM養成マガジン(無料版)」、「PM養成マガジンプロフェッショナル(有料版)」や「コンセプチュアル・マネジメント(無料」、書籍出版、雑誌記事などで積極的に情報発信をし、プロジェクトマネジメント業界にも強い影響を与え続けている。
メルマガ紹介
本連載は、PMstyleメールマガジン購読にて、最新記事を読むことができます。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

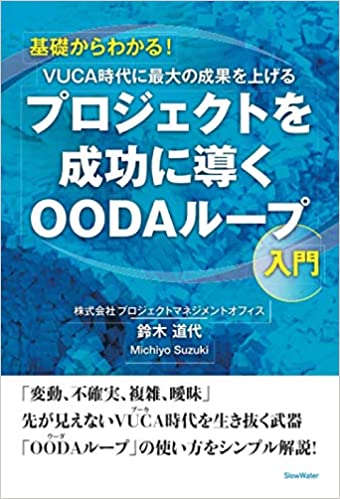
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/06/17,19☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/6/11☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/4/1☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/12☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/18☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/27,29☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/5/28☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索