イノベーションにワクワク感はなく、主体的にできる、成果が実感できる時に人はワクワクするそうだ。が。ワクワクしないとイノベーションはできない。主体的にできる、成果が実感できることは承認欲求であり、内発的動機ではない
第44回 なぜ、イノベーションはワクワクしないのか(2014.07.16)
プロジェクトマネジメントオフィス 好川 哲人
◆イノベーションにワクワク感はない
4年くらい前に、「プロジェティスタ研究会」という研究会をやっていて、その研究会主催で「仕事をワクワクする」というテーマでワールドカフェを行ったことがある。ワクワクというのは、内発的な動機、ダニエル・ピンクのいうところのモチベーション3.0である。東京で2回、関西で1回行った。そのときに印象に残ったのは、ワクワクする状況として、新しいことをやるとか、社会に貢献するといったワードが少なかったことだ。逆に
・主体的にできる
・成果が実感できる
といった発言が多かった。研究会としては、これを承認欲求であり、内発的動機ではないと判断した。
つい最近、ある場で同じような話を聞いた。「イノベーション」という言葉にはワクワク感を感じないという話だ。ずっと頭のどこかに引っかかっていた話だったので、やっぱりそうかというのが正直なところだった。
僕はもともと技術者なので、(いろいろなレベルがあるが)人がやってしまったことは興味がないとか、社会に役立たないことはやりたくないといった発想が強い。だから、イノベーションという言葉には社会に影響を与えるという意味でワクワク感を感じるし、感じない人の感覚は理解できない。
◆イノベーションがワクワクしない理由
もちろん、理屈ではそれなりに分かる。企業でイノベーションを起こそうという場合には、主体性が持てない場合が多い。社長がやれと言っているので何かやらなくてはならないという受動的なケース多い。だからといって、目の前の仕事がなくなるわけではない。社長がなんと言おうと、自分の評価者の優先順位は目先の業績にある。だから、今期の予算を達成した上で、やってくれという話にしかならない。
評価されないからといって自分の好きなようにできるわけではない。予算がつけばラッキーで、当面はコストなので予算がつかないことすらある。新しい製品を作ろうとしても、自分たちだけで作れる訳ではなく、定常業務をやっている人の協力が不可欠で、これもいい顔をされない。
開発がうまくいけば、既存の事業との調整が必要になるので、既存事業をやっている人からは警戒される。自分が携わっている既存事業との調整が必要になる場合も少なくない。
こんな状況の中で、自分がやりたいわけでもないことをやることがワクワクするはずがないという話だ。だから関わらなくて済むというものでもないので、やらされ感が一層増すという構図なのだろう。
◆ワクワクしないとイノベーションはできない
上に述べた・評価されない
・定常業務の方が優先される
・既存事業との調整が必要
といった問題はイノベーション云々とは関係なく大問題で、ましてやそこに、イノベーションの成果の不確実性が加わると内発的な動機がないと乗り越えることはできないだろう。
では、イノベーションをワクワクに変えるにはどうすればよいのだろうか?難しい問題だし、決定的な方法があるわけではないと思うが、最近感じていることを一つだけ書いておく。
◆知識がワクワク感を生む
理由はいろいろとあるのだろうけど、ビジネスに対する知識不足があるのではないかと思う。たとえば、自分の関わっているビジネスの戦略を作れない人にカイゼンはできてもイノベーションができるとは思えない(言葉の定義は察してほしい)。自分の関わっているビジネスを徹底的に知ることだ。経験するという意味ではなく、知識を蓄積するという意味だ。国内の状況は意識をしなくても分かることが多いが、たとえば、どんなトレンドがあるが、海外の競合はどんなことをやっているか、自分たちのやっているビジネスの生まれた経緯や歴史などは意識しないと分からない。
自分が経験している範囲で知っていることからできることはたいていやっている。自分ができることをやる範囲を広げるには新しいことを知ることが必要だ。顧客についてもそうだ。顧客の現実だけではなく、顧客に関係する知識がとれだけあるかで、想像の範囲は大幅に変わってくる。
日本の企業は経験主義なのでこのような発想にはあまりならないが、目の前だけ見ていても想像力はうまれない。知識があってはじめて今いる枠を飛び越える想像力が働く。
◆関連セミナー
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆イノベーション力を身につける ◆(7PDU's)
日時・場所:【Zoom】2026年 05月 08日(金)9:30-17:30(9:20入室可)
※Zoomによるオンライン開催です
※ハーフセミナーは、事前学習3時間あります
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木道代(プロジェクトマネジメントオフィス、PMP、PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/innov_skill2.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「イノベーションを生み出す力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.イノベーション力の3つの軸
2.アイデアを生み出すマインド
(演習)テーマを決める
3.アイデアを生み出す思考法
(演習)アイデアを生み出す
4.アイデアを実現する行動
(演習)アイデアの実現方法を考える
5.まとめ〜アイデアを解放する
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆質問力はこちら
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆問いから始まるイノベーション ◆(7PDU's)
日時・場所:【Zoom】2026年 06月 11日(木)9:30-17:30(9:20入室可)
※Zoomによるオンライン開催です
※ハーフセミナーは、事前学習3時間あります
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木道代(プロジェクトマネジメントオフィス、PMP、PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/inquir2.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「イノベーションを生み出す質問力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.質問がイノベーションを生む
2.誰に質問するのか
3.質問の構造と技術
(演習)パワークエスチョンを作る
4.イノベーションを生む質問
(演習)挑発的な質問、破壊的な質問を作る
5.質問力を養うには
6.イノベーションの場を作る
7.質問ストーミング(ワークショップ)
(演習)質問ストーミングで質問を作る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者紹介
好川哲人、MBA、技術士
株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表、PMstyleプロデューサー
15年以上に渡り、技術経営のコンサルタントとして活躍。プロジェクトマネジメントを中心にした幅広いコンサルティングを得意とし、多くの、新規事業開発、研究開発、商品開発、システムインテグレーションなどのプロジェクトを成功に導く。
1万人以上が購読するプロジェクトマネジャー向けのメールマガジン「PM養成マガジン(無料版)」、「PM養成マガジンプロフェッショナル(有料版)」や「コンセプチュアル・マネジメント(無料」、書籍出版、雑誌記事などで積極的に情報発信をし、プロジェクトマネジメント業界にも強い影響を与え続けている。
メルマガ紹介
本連載は、コンセプチュアル・マネジメント購読にて、最新の記事を読むことができます。
コンサルティングメニュー紹介
PMOコンサルティング、PMOアウトソーシングサービス、人材マネジメントサービスなど、御社に最適のコンサルティングをご提案させていただきます。まずは、お問合せください。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

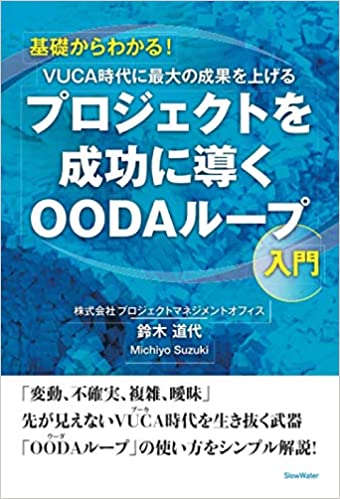
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/02/25,27☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/6/11☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/2/25☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/12☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/18☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/27,29☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/5/28☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索