従来業務が大切で、失敗しないことがすべてだという価値観だけでは、現実問題としてジリ貧になり、イノベーションに人材を充てることができない。そして、今後生き延びていくことは難しい
第17話 失敗のジレンマとその解決法(2013.04.22)
プロジェクトマネジメントオフィス 好川 哲人
◆イノベーションは評価されない仕事?
前回、イノベーションプロジェクトの中止について話をしたが、中止をどのように扱うかというのと同じくらい難しい話が、「失敗」の話である。イノベーションでは失敗を認めなくてはだめだという議論がある。観念的にはそのとおりなのだが、この話はそんなに単純な話ではない。失敗の仕方の問題で、全力を尽くして失敗したのと、適当にやって失敗したのでは全く意味が違う。適当というのは、自分がそこに投入できる時間の中で全力を尽くすという意味だと思ってほしい。
イノベーションのようなテーマをやるのに適当にやる人はいないだろうと思う人がいるようだが、これが実に多い。むしろ、適当にやる人の方が多いかもしれない。これは、評価の問題が絡んでくるが、イノベーションは難しさの割には評価されない一面がある。
◆失敗が許容できる仕事は評価されない仕事
日本組織は失敗を許さないという特性があるが、言い換えると、重要な仕事は失敗してはならず、高く評価するということである。高く評価されるということは優先順位が高いということでもある。
目 の前に、リスクの小さいが高く評価される仕事と、リスクが大きいがあまり評価されない仕事があったら、あなたならどちらを選ぶだろうか。大抵の人は前者を 選ぶのではないだろうか?これがイノベーション業務が適当に行われる理由である。高く評価される仕事なら、残業をしてでもやろうと思うが、高く評価されない仕事ではあればそこまではやらない人が多いと思う。
仮に失敗を許容することができるようになったとして、失敗を許容するといった瞬間にその仕事は評価されなくなるといったロジックがあることを頭の片隅に残しておいてほしい。
◆人材の問題
さらにこの問題を複雑にしているのが、人材の問題である。人材マネジメントとして、重要だと考える仕事には、評価の高い人(あまり好きな言葉ではないが、簡単のためにA級人材とよぶ)をアサインする。高く評価しない仕事には、評価の高くない人(B級人材)をアサインする。
実際にこの問題は起こっている。経営者層からイノベーションをいうお題が降りてきたときにA級人材を当てる管理者はほとんどいない。失敗しても言い訳ができるし、成果が出るとは限らない仕事にA級人材を当てる理由はない。A級人材には確実に成果の出る仕事をさせたい。つまり上で述べた高く評価する仕事を担当させたいと思うわけだ。
そこで、イノベーション業務はB級人材に担当させることになる。ここで、失敗することが許容できるかという問題が 出てくる。A級人材が取り組んで失敗したならどのようにやっても失敗しただろうと思えるかもしれないが、B級人材の場合、もっとうまくやる方法があったのではないかと考え、失敗を許容できない。
◆ジレンマ
ここに、A級人材を投入できないので、失敗を許容できないというジレンマが生じる。トータルで見ると、失敗してもよい仕事はたいして重要な仕事ではなく、B級人材で対応しようとするが、それによって失敗を許容しにくくなるというジレンマが生じる。失敗を認めればよいという問題は一見単純な問題のように見えるが、日本の組織の場合には多くの組織でこのようなジレンマを抱えている問題である。そして、ジ レンマの解消方法として、失敗しない範囲でやるという決着を見ることが多い。その時点でイノベーションとは言い難い活動になっている。
◆ジレンマの原因
さて、このジレンマはどうして生じるのかを考えてみよう。理由は2つある。一つは、重要な仕事は失敗してはならないという前提である。この前提は定常業務の中では正しいが、イノベーションでは正しいとはいえない。二 つ目は、人材の評価である。いま、A級人材は例外的に絶対能力が高い人材はいるとしても、基本的にはこれまでの正解のある環境で効率よく成果を出してきた 人材である。そして戦略的重要性の高い定常業務を担当して、成果を出している。この評価はこの評価でいいと思うのだが、イノベーションにおいて効率がA級な人材がA級として機能するとは限らない。
そう考えると、新規性や創造性が必要とされるイノベーションでは、従来の評価を持ち込んでみても始まらない。
◆失敗を成果として評価する
こ のような前提で考えたときに、失敗を許容できるA級の人材をイノベーションには当てるべきである。そして、失敗したことを評価すべきなのだ。進捗管理のところで述べたように、失敗の個数が多くなればなるほど、進捗が進んでいることになると考え、失敗を成果として評価するのだ。そんな人事をしていると、組織が持たないという声が聞こえてきそうだが、今の従来業務が大切で、失敗しないことがすべてだという価値観だけでは、現実問題としてジリ貧になっており、今後生き延びていくことは難しいだろう。
◆関連セミナー
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆コンセプチュアルな組織を創るマネジメント ◆(7PDU's)
日時・場所:【Zoom】2025年 01月 22日(水)9:30-17:30(9:20入室可)
【Zoomハーフ】2023年 03月 15日(水)13:00-17:00+3時間
※Zoomによるオンライン開催です
※ハーフセミナーは、事前学習3時間あります
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木道代(プロジェクトマネジメントオフィス、PMP、PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/conceptual_management.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「コンセプチュアルスキルとは(前半)」「コンセプチュアルスキルで行動が変わる」
「イノベーションを生み出す力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.コンセプチュアルではない組織の問題点
・個人レベルの問題点
・チームレベルの問題点
・組織レベルの問題点
2.コンセプチュアルなマネジメントのポイント
2.1 質問型の組織を創る
2.2 コンセプチュアルな組織活動のプラニング
2.3 ステークホルダーへのコンセプチュアルな対応
2.4 コンセプチュアルな人材育成
2.5 コンセプチュアルな組織文化の構築
3.コンセプチュアルなマネジメントの目標
4.コンセプチュアルマネジメントでコンセプチュアルな組織を創る仕組みワークショップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者紹介
好川哲人、MBA、技術士
株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表、PMstyleプロデューサー
15年以上に渡り、技術経営のコンサルタントとして活躍。プロジェクトマネジメントを中心にした幅広いコンサルティングを得意とし、多くの、新規事業開発、研究開発、商品開発、システムインテグレーションなどのプロジェクトを成功に導く。
1万人以上が購読するプロジェクトマネジャー向けのメールマガジン「PM養成マガジン(無料版)」、「PM養成マガジンプロフェッショナル(有料版)」や「コンセプチュアル・マネジメント(無料」、書籍出版、雑誌記事などで積極的に情報発信をし、プロジェクトマネジメント業界にも強い影響を与え続けている。
メルマガ紹介
本連載は終了していますが、コンセプチュアル・マネジメント購読にて、最新の関連記事を読むことができます。
コンサルティングメニュー紹介
PMOコンサルティング、PMOアウトソーシングサービス、人材マネジメントサービスなど、御社に最適のコンサルティングをご提案させていただきます。まずは、お問合せください。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

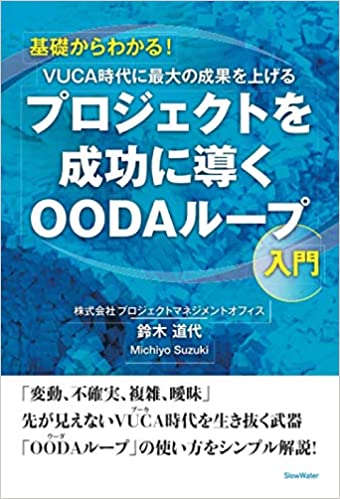
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/02/25,27☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/2/19☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/2/25☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/16☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/2/18☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/2/18,20☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/2/20☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/2/21☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索