イノベーション実践、コンセプチュアルスキル、プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、PMOについての最先端の情報、研修、セミナー、コンサルティングをお届けします。
第5回 いかに周囲の協力を得るか? カレンシーの交換(2008.07.27)
インフルエンス・テクノロジーLLC 高嶋 成豪
私の第2回目の記事で、レシプロシティについて触れました。
第2回 何が人を動かすのか
何かを受け取ったらお返ししなければならないと感じる社会通念のことです。今、ちょうど夏の贈り物の季節ですね。先日、思わぬ方からお中元をいただいてしまい、出遅れていた私は、慌ててお返しを用意しました。このように慌ててしまうのは、レシプロシティが働いているからです。このレシプロシティという社会通念は、人間社会に古今東西見られるもの。そのうえとても強力です。この流れに逆らえば、その人間関係の中で生きていくのは難しくなるからです。「あいつは挨拶しても返事もしない」「せめて言われたことを真っ先にやってくれればいいのに」などといわれて、徐々に仲間はずれにされたりします。逆にちゃんとお返しする人、言い換えると約束を守る人、期待に違わぬ良い仕事をする人、こちらの苦労をわかってくれる人などは、周囲から信頼され、人々が集まってくるのですね。 レシプロシティの原則からすると、すぐに周囲の協力を得られるプロジェクトマネジャーや、カリスマなどといわれるリーダーは、「この人にお返ししなければ」と感じている人が大勢いる、ということもできるのです。
ここでよく考えなければならないのは、相手が「受け取った」と感じること。相手にとって「これはありがたい」と感じられれば、相手の協力を得られる可能性は、ぐっと高まります。しかし、こちらがどんなに良いものを手渡したつもりであっても、それに価値を感じなければ相手は受け取ったと思わない。それどころかありがた迷惑だなどと思われてしまう。これではあなたに「お返ししよう」などという気になりません。こちらが求める何かを得ようと思ったら、相手が価値を感じる何かを渡す必要があります。そこでは相手が同じ程度の価値があると感じるもの同士が交換されるので、それを通貨にたとえて「カレンシー」、そのやり取りを「カレンシーの交換」と呼びます。「影響力の法則」の著者、アラン・コーエンとデビッド・ブラッドフォードによれば、これが相手を動かす基本的なメカニズムです。
このメカニズムを最大限に有効に使うには、相手が価値を感じる何かをつかんでおく必要があります。それは予算の達成かもしれないし、プロジェクトの期限内の終了かもしれない。品質基準を満たすこと、上司に認められることかもしれない。部下たちの成長に価値を置くマネジャーもいる。専門技術の向上やキャリアップに価値を感じるメンバーも少なくない。多くは、その人の置かれている立場を理解すれば、読めてくることです。必ずしも相手の性格まで読まなくてもよいのです。私たちはうまくいかない相手の性格は悪く感じ、うまくいっていると良い人に思えるものです(第3回の記事参照)。
第3回 否定的サイクルを脱する
最初から答えは出ているようなもの。それよりも、その人が置かれている立場にいたら、何をありがたいと思うだろうかと考える。ひょっとしたら、組織の中で孤独だったりすると、心を許せるような人間関係自体に価値を置くことも少なくない。組織の中では一般的に上に行くほど、孤独ですね。下の方にも孤独な人はいます。
こうして相手が何に価値を感じるかをつかめれば、こちらが手渡すカレンシーを用意すればよいのですが、しばしばそう簡単にはいきません。このときの落とし穴は、こちらにカレンシーがないと決めつけてしまい、早々にあきらめてしまうことです。
(部下たちのモチベーションを高めたい開発課長) F氏は、あるメーカーの基幹製品の開発課長で、複数のプロジェクトの責任者でもあります。近年、基幹製品といえどもお客様のニーズが刻々と変わってしまい、なかなか技術的な方向性を打ち出せませんでした。お客様や会社からのプレッシャーが強まる中で、部下たちのモチベーションはいまひとつ高まりません。予算は限られており、報奨金や昇給も期待できません。F氏自身は、この分野の技術には誰にも負けないという自負があります。しかし、
今はリソースが不足しています。毎日忙しさに気を紛らせ、問題を先送りするF氏です。
F氏のように「金があれば」「権限があれば」と考える人は少なくありません。私たちは、金や権限がなければ人を動かせないと感じがち。特にプレッシャーが強まってくるとそう感じるような気がします。確かに、金や昇進は大きなカレンシーになりえます。しかし、現実には金にそれほど価値を感じない人もいます。ボーナスが増えたからといって、その分もっと働こうなどという人は、今では少ないでしょう。それよりも、他の何かに価値を感じないだろうか。「影響力の法則」では、組織で使える次のようなカレンシーが紹介されています。 1.気持ちを高揚させるもの 2.仕事そのものにやくだつもの 3.立場に関するもの 4.対人関係に関するもの 5.その人自身に関するもの たとえば、もっと面白い仕事や情報の機会、人脈、アイデアを聴いてくれること、コーチングしてくれること、わくわくするようなビジョン、孤独を紛らす話し相手などなど。実は私たちが想像する以上に、カレンシーとして使えるものには多くの選択肢があります。その中で得意なものを使う。また今まで使ったことはないけれども、これで相手が動くなら、思い切って使ってみる。
協力を得たい相手が、上司であっても、部下であっても、他部門のマネジャーであっても、あるいは協力会社の責任者であっても、協力者に恵まれるプロジェクトマネジャーの方々は、彼らと頻繁にカレンシーの交換を行っています。そのためにも、カレンシーの選択肢を増やしておくと良いのです。それは、誰にでもできること。すごいことをやらなくても、多くはすでに持っているものを使えばよいのです。
◆「影響力の法則(R)」を使ったセミナーを開催します
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践◆7PDU's
日時・場所:【Zoom】2026年 05月 19日(火)9:30-17:30(9:20入室可)
【Zoomハーフ】2026年 03月 07日(土)13:00-17:00+3時間
【Zoomナイト】2026年 04月 15日(水)17日(金) 19:00-21:00+3時間
※Zoomによるオンライン開催です
※ナイトセミナーは、2日間です
※ハーフセミナー、ナイトセミナーは、事前学習が3時間あります。
※少人数、双方向にて、ディスカッション、ロールプレイを行います
講師:鈴木道代(株式会社プロジェクトマネジメントオフィス,PMP,PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/influence20.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube動画「ステークホルダーマネジメント」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.ステークホルダーマネジメントとは何か
・ステークホルダーに動いてもらう
・ステークホルダー・エンゲージメント・マネジメント
2.ステークホルダーの特定・プロジェクトのパラメータ
・ステークホルダー・マトリクス
・ステークホルダー影響グリッド
・ステークホルダー・マネジメント戦略
・(演習2)ステークホルダーリスト
3.影響力の法則(R) ・影響力とは何か?
・「カレンシーの交換」メカニズム
・ステークホルダーの目標を把握し、カレンシーを計画するステップを学ぶ
・(演習3)カレンシーを考える
4.概念的に考えて具体的に行動する・コンセプチュアルスキルとは
・本質を見極める
・洞察力を高める
5.ステークホルダーと良い関係を作る・WinWinの関係
・信頼を得る
・チームを結束させる
・(演習5)期待と要求のロールプレイ
6.まとめ
・(演習6)カレンシーを再考する
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者紹介
高嶋 成豪 インフルエンス・テクノロジーLLC マネージング・パートナー
人材開発/組織開発コンサルタント。インフルエンス・テクノロジーLLC.マネージング・パートナー。ゼネラル・モーターズ、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどで人材開発に従事。現在リーダーシップ、コミュニケーション、チームビルディング、キャリア開発のセミナーを実施し、年間約1000名の参加者にプログラムを提供している。ウィルソンラーニング・ワールドワイド社によるリーダーシッププログラム、LFG(Leading for Growth:原著はコーエン&ブラッドフォード両博士の共著“Power Up”)のマスター・トレーナー。2007年『影響力の法則 現代組織を生き抜くバイブル』(原題“Influence without Authority”)を邦訳。コーエン&ブラッドフォード両博士から指導を受け、「影響力の法則」セミナー日本語版を開発。日本で唯一の認定プロバイダー。筑波大大学院教育研究科修了 修士(カウンセリング) 日本心理学会会員 ISPI(the International Society for Performance Improvement)会員 フェリス女学院大学講師
メルマガ紹介
本連載は終了していますが、PM養成マガジン購読にて、最新の関連記事を読むことができます。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

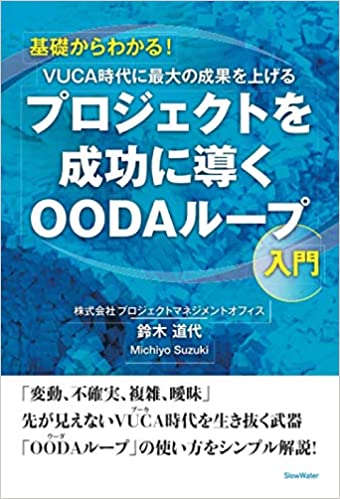
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/02/25,27☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/2/19☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/2/25☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/16☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/2/18☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/2/18,20☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/2/20☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/2/21☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索