イノベーション実践、コンセプチュアルスキル、プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、PMOについての最先端の情報、研修、セミナー、コンサルティングをお届けします。
第3回 プロダクトマネジメントにおける「インテリジェンス」(2012.10.30) 2/2
新井 宏征
◆競合分析を超え、顧客を理解する
これら3つの項目の分析は、すでにさまざまな手法が紹介されている。例えば、市場分析ではPESTと呼ばれるフレームワークが良く知られている。これは、”Political(政治), Economic(経済), Social(社会), Technological(技術面)analysis”の頭文字を取ったもので、企業を取り巻くマクロな環境を分析するためのフレームワークである。また3Cと呼ばれるフレームワークは「顧客(Customer)分析」と「競合(Competitor)/自社(Company)分析」を表すものとして知られている。
ただし、これらの分析をしっかりやって戦略を作っても、それがうまく機能するとは限らない。もちろん、戦略を策定するのと実行するのは別だからという議論もあるが、それ以前に、これまでのように競合を分析し、顧客を分析した上で、練られた戦略を元に製品やサービスを投入しても、顧客に受け容れられないという事態が起きている。
そのような事態を引き起こす要因はさまざまだが、そのうちのひとつに競合を意識し過ぎ、顧客を理解できていない(あるいは理解したつもりになっている)というのがあるだろう。
新規製品やサービスを市場に投入する時だけではなく、すでに市場に投入した製品やサービスの戦略を考える上でも、たしかに競合分析は重要である。しかし、競合分析の結果、競合を意識し過ぎると、競合と自社との差分に意識がいきがちになり、その差分を埋めようと努力を始めてしまう傾向がある。プロダクトマネジメントにおける顧客の存在を考える上で有益な示唆を与えてくれる『Subject To Change ―予測不可能な世界で最高の製品とサービスを作る』 では「他のみんなが修得したことの上達を目標にすることを戦略とは呼ばない」と、企業が「対等のわな」に陥ることをいさめている。
同書では、さらに従来型の顧客分析の限界についても指摘している。それに代わるものとしてエスノグラフィーをはじめとする、顧客の体験を理解するための手法を紹介し、顧客に「共感」することを強調している。エスノグラフィーとは、元々、文化人類学などで用いられていた手法で、フィールドワークを通して、観察結果から知見を引き出すことを目的としたものである。
いわゆる先進国では、近年になってものがあふれ、顧客自身が欲しいものがわからないという状態になっている。このような市場において、従来のように、性別や年齢といったデモグラフィック(人口統計学)情報を元にしたセグメンテーションを行い、特定のセグメントに対して行ったアンケート結果だけから顧客のニーズを把握することは困難になってきた(もちろん、そのような調査は決して無駄ではないし、『Subject to Change』でも従来型の手法と組み合わせて使うことを推奨している)。
そのような中で注目されているのが「デザイン思考」と呼ばれる手法である。デザイン思考の手法を用いたコンサルティングを提供しているIDEO社CEOのティム・ブラウンは、『デザイン思考が世界を変える』という著書の中で「デザイナーである」ことと「デザイナーのごとく思考する」ことの違いを理解するまでにずいぶんと時間がかかったということを述べている。
ここからわかるように「デザイン思考」と「デザイン」は別のものである。デザイン思考については、近年、多くの書籍が出ているし、Web上でもさまざまな記事があるので、詳しくはそちらを参照していただきたいが、簡単に言えば、顧客の観察を通してアイデアを生み出し、そのアイデアをプロトタイプを通して評価するというプロセスを繰り返していくことで、イノベーションにつなげていくための手法である。
図で示しているのは、セオドア・レビットが提唱し、その後、ジェフリー・ムーアが『キャズム』等の著書でも紹介している「ホールプロダクト」という概念とそれぞれの段階に相当する例を示したものである。これは顧客に提供する製品は、実際に提供される「コアプロダクト」だけではなく、さまざまな周辺機器や補完サービスなどを組み合わせることで、「完全な製品」となるということを意味している。「デザイン思考」などの手法をとおして顧客を観察するという手法は、「コアプロダクト」だけに目がいきがちな視点を「ホールプロダクト」としてとらえることができる助けとなるものではないかと考えている。
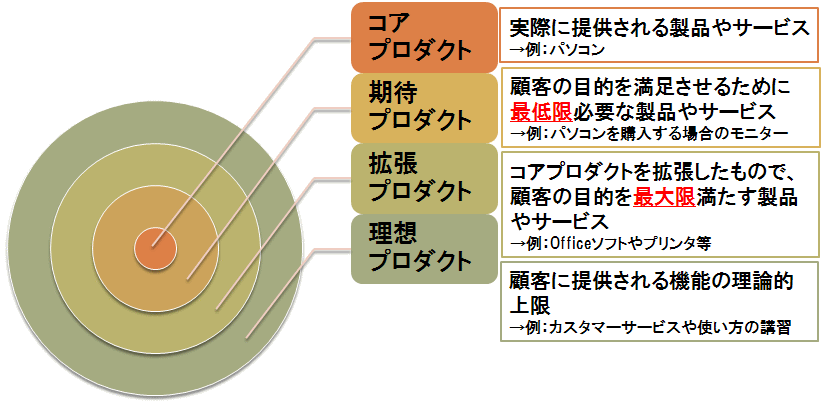
◆「顧客を理解する」組織にするには
「デザイン思考」のような顧客を理解するための手法は、注目を集めてはいるものの、実際に期待するようなイノベーションを起こすまでに至らず、十分に利用されていない点も指摘されている。
これはティム・ブラウンが先ほども紹介した『デザイン思考が世界を変える』で、「IDEOを意気揚々と訪れ、「次なるiPodを作ってくれ」と言い放つクライアントは数知れないが、それを聞いたデザイナーたちが「それなら次なるスティーブ・ジョブズを用意してくれ」と(小声で)つぶやくのも同じくらい耳にしている」と書いているように、「デザイン思考」という手法そのものがイノベーションを起こすわけではない。「デザイン思考」を実践する組織を作っていくことが、最終的には必要になってくる。また、『Subject To Change』の中ではエスノグラフィーなどを用いた調査を「組織コンピテンシー」として扱うべきだと主張している。
これまで紹介してきたように、時代の変化に伴い、「インテリジェンス」に求められる役割も変わってきている。次々と登場する新しいコンセプトをつまみ食いするのではなく、それらをプロダクトマネジメントのプロセスの中に組み込み、組織の中で定着させることによってはじめて、それらがイノベーションにつながる「インテリジェンス」になり得るのである。
著者紹介
新井 宏征
SAPジャパンにて、BI関連のソフトウェア導入業務に従事した後、2007年よりシンクタンク勤務後、2013年に独立。主に法人関連分野のコンサルティング業務に従事。主な著書に『スマートグリッドの国際標準と最新動向2012』、『グーグルのグリーン戦略』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『90日変革モデル』などがある。
Facebook上でプロダクトマネジメントのグループも管理している。
メルマガ紹介
本連載は終了していますが、PM養成マガジン購読にて、最新の関連記事を読むことができます。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

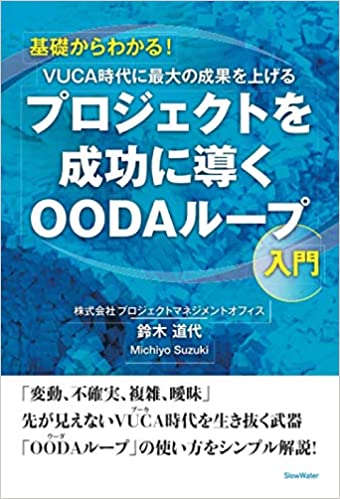
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/06/17,19☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/6/11☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/4/1☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/12☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/18☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/27,29☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/5/28☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索