潜在的な部分も含めたプロジェクト要求の把握が、プロジェクト(マネジメント)品質の鍵を握る
第6回 プロジェクト要求をどのように収集するのか?(2008.12.12)
プロジェクトマネジメントオフィス 好川 哲人
◆プロジェクト品質という考え方
前回は、ステークホルダ、ゴール、スコープの関係について説明した。そこで述べたように、切り口を決めてそこからこの三角関係に切り込んでいくことになるが、どこから切り込むかによって目的(戦略)達成の度合いが全然変わってくる。
このことを念頭において、プロジェクトマネジメントの目的というのを改めて考えてみよう。プロジェクトを実施する場合に、もっとも重要なのは「プロジェクト品質」という概念である。プロジェクト品質は、プロジェクトで開発するプロダクトの品質だけではなく、プロジェクトマネジメントにかかわる品質を問うものだ。したがって、いくら完璧な製品やシステムを作っても、納期から遅れていたり、あるいは、当初想定した原価を超えていたりすればプロジェクトの品質は低くなる。もちろん、コストや納期のようなはっきりしたものだけではなく、顧客満足(CS)やメンバーの満足(ES)も品質として評価されるし、さらに言えば、プロジェクトで如何にリスクを発生させなかったかとか、如何にコミュニケーションがうまくできたか、如何に効率の良い調達ができたかといったことも評価の対象になる。
このようにプロジェクトマネジメントの品質、つまり、どれだけ計画通りにプロジェクトを進めることができたかをプロジェクト品質と呼ぶ。プロジェクトマネジメントというのはつまるところ、プロジェクト品質を少しでも向上させることが目的であり、その延長線上にプロジェクトを成功させることがあるのだ。
◆プロジェクト要求がプロジェクト品質の鍵を握る
さて、このプロジェクト品質にもっとも大きく影響してくるのが前回述べたプロジェクト要求であり、プロジェクト要求を持っているのがステークホルダである。したがってプロジェクト品質を高めるためには、要求をうまく引き出していくことが重要である。
ここで注意した方がよいのは、要求を持っているといっても潜在的に持っているケースが多い。つまり、要求には
(1)ステークホルダ自身が意識し、顕在化している要求
以外に
(2)ステークホルダ自身が意識はしているが、顕在化はしていないもの
(3)ステークホルダ自身が気がついていないもの
の2つがある。プロジェクトにもよるが、(3)の要求が重要なケースも少なくない。
したがって、要求の分析の際に答えを探すように態度で臨むと、(1)や(2)の要求しか引き出せず、失敗する可能性が高くなる。
さらに話を複雑にしているのは、前回述べたように要求は、ステークホルダによって整合性のない(対立する)ものが多いことだ。たとえば、社内ステークホルダでいえば、営業部長はできるだけ早くほしいと思っているが、技術部長はしっかりした商品を作りたいと思っているといったことだ。
◆プロジェクト要求の収集法
では、実際に要求の分析方法にはどのようなものがあるのか?上のように考えた場合に、ステークホルダや顧客自身から情報として得られるものとそうでないものがあると考えると、両方の側面からのアプローチが必要である。
ひとつのアプローチはステークホルダから情報を得るための方法である。これには、
・顧客の声
・調査票
・既存のもの(システム、商品)の分析
・インタフェース(ユーザ)の研究
・ファシリテーションセッション
・ブレーンストーミング
などの方法がある。これに対して、外部から情報を得て、ステークホルダにぶつけることによって要求を引き出す方法としては
・マーケティングリサーチ
・ベストプラクティスの評価
などをあげることができる。また、もうひとつのやり方は、ステークホルダ(特に顧客)を観察することによって、ステークホルダが顕在化しきれていない要求を引き出す方法がある。この方法としては
・プロトタイピング
・フォーカスグループ
・観察
などをあげることができる。
◆ステークホルダーマネジメントのセミナーを開催します。
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践◆7PDU's
日時・場所:【Zoom】2026年 05月 19日(火)9:30-17:30(9:20入室可)
【Zoomハーフ】2026年 03月 07日(土)13:00-17:00+3時間
【Zoomナイト】2026年 04月 15日(水)17日(金) 19:00-21:00+3時間
※Zoomによるオンライン開催です
※ナイトセミナーは、2日間です
※ハーフセミナー、ナイトセミナーは、事前学習が3時間あります。
※少人数、双方向にて、ディスカッション、ロールプレイを行います
講師:鈴木道代(株式会社プロジェクトマネジメントオフィス,PMP,PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/influence20.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube動画「ステークホルダーマネジメント」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.ステークホルダーマネジメントとは何か
2.ステークホルダーの特定
・(演習2)ステークホルダーリスト
3.影響力の法則(R) ・影響力とは何か?
・(演習3)カレンシーを考える
4.概念的に考えて具体的に行動する・コンセプチュアルスキルとは
・本質を見極める
・洞察力を高める
5.ステークホルダーと良い関係を作る
・(演習5)期待と要求のロールプレイ
6.まとめ
・(演習6)カレンシーを再考する
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者紹介
好川哲人、MBA、技術士
株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表、PMstyleプロデューサー
15年以上に渡り、技術経営のコンサルタントとして活躍。プロジェクトマネジメントを中心にした幅広いコンサルティングを得意とし、多くの、新規事業開発、研究開発、商品開発、システムインテグレーションなどのプロジェクトを成功に導く。
1万人以上が購読するプロジェクトマネジャー向けのメールマガジン「PM養成マガジン(無料版)」、「PM養成マガジンプロフェッショナル(有料版)」や「コンセプチュアル・マネジメント(無料」、書籍出版、雑誌記事などで積極的に情報発信をし、プロジェクトマネジメント業界にも強い影響を与え続けている。
メルマガ紹介
本連載は、PM養成マガジン購読にて、最新記事を読むことができます。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

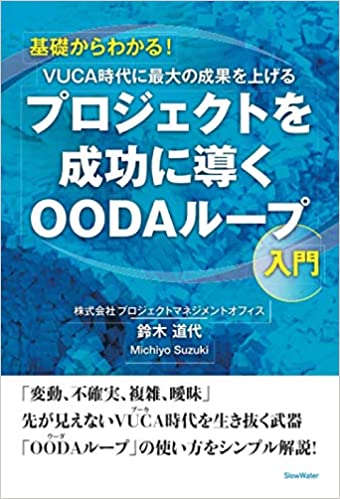
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/02/25,27☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/6/11☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/2/25☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/12☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/18☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/27,29☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/5/28☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索