イノベーション実践、コンセプチュアルスキル、プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、PMOについての最先端の情報、研修、セミナー、コンサルティングをお届けします。
第2回 逆ピラミッドとプログラムマネジメント(2008.09.05)
プロジェクトマネジメントオフィス 好川 哲人
◆顧客満足を実現する逆ピラミッド
プロジェクトは現場の活動である。プロジェクトの先には顧客や、営業部門、さらにその先には真の顧客であるエンドユーザがいる。顧客やエンドユーザが満足するプロジェクトをしようとすれば、経営組織のピラミッドを逆にしなくてはならない。
通常の経営組織のピラミッドは、トップに経営陣(エグゼクティブマネジャー)がおり、その下にシニアマネジャー、さらにはミドルマネジャーがいる。そして現場リーダー(プロジェクトマネジャー・リーダー)がいて、現場(プロジェクト)がある。社内ラインはここまでで、このピラミッドで顧客や市場に対応していくことになる。
必然的にもっとも接点が多くなるのはプロジェクト(現場)である。かつ、プロジェクトの場合、社を代表する立場でカウンターパート関係なしに、外部との接点が出てくることも珍しくない。
そのように考えると、顧客を満足させるために必要なことはおのずと決まってくる。組織全体が、プロジェクトが顧客を満足させる活動ができるようにサポートすることである。現場リーダーはプロジェクトのメンバーを全力をあげてサポートする。ミドルマネジャーは現場リーダーを全力でサポートする。シニアマネジャーはミドルマネジャーを全力サポートする。そして、エグゼクティブはシニアマネジャーをサポート
る。このような体制が必要である。このような関係を逆ピラミッドと呼ぶことがある。
◆機能しない逆ピラミッド
ところが、逆ピラミッドというのはあまりうまく機能していないケースが多い。特に、現場とのインタフェースのところがうまく機能していないことが多い。なぜだろうか?
ミドルマネジャーの仕事は、「部下の成果を最大化すること」である。自身もプレイしているのでそんな時間はないかもしれないが、そうだとしたら、ミドルのレベルでの業務の組み立てがまずいのではないかと思う。今までのやり方をしていたら、プレイングマネジャーは確かに成果主義は現場に目配りする余裕はないというのはよくわかる。あまり、関連性のない仕事をばらばらにしている。その中の一つに自身の仕事もある。このような事業の組み立てをすると、当然ながら、自分の仕事を優先し、余裕のある中で部下の指導をするというなるのは自然なことだろう。
◆プログラムマネジメントがミドルの成果を最大化する
そこで、自分の仕事の組み立てそのものを変える必要がある。
どう変えるか?プログラムマネジメントにより、部下の成果を最大化することにより、自らの成果を最大化できるような構造を作り上げていくことである。
これは、プログラムとして仕事を定義していくことに他ならない。ミドルマネジメントが担当する範囲は、課かもしれないし、商品群かもしれない。あるいは、顧客かもしれないし、場合によってはミッションの明確なプログラムを担当するかもしれない。いずれにしても、戦略を明確に持ち、プログラム化し、プログラムベネフィットを最大化することを目指さなくてはならない。
◆関連するセミナーを開催します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント ◆7PDU's
日時・場所:【Zoom】2026年 02月 16日(月)9:30-17:30(9:20入室可)
【Zoomハーフ】2026年 03月 28日(土)13:00-17:00+3時間
【Zoomナイト】2026年 04月 08日(水)10日(金) 19:00-21:00+3時間
※Zoomによるオンライン開催です
※ナイトセミナーは、2日間です
※ハーフセミナー、ナイトセミナーは、事前学習が3時間あります。
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木道代(プロジェクトマネジメントオフィス,PMP,PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/conceptual_pm.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「コンセプチュアルスキルとは(前半)」「コンセプチュアルスキルで行動が変わる」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.VUCA時代に必要なコンセプチュアルなプロジェクトマネジメント
2.プロジェクトへの要求の本質を反映したコンセプトを創る
3.コンセプトを実現する目的と目標の決定
4.本質的な目標を優先する計画
5.プロジェクトマネジメント計画を活用した柔軟なプロジェクト運営
6.トラブルの本質を見極め、対応する
7.経験を活かしてプロジェクトを成功させる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者紹介
好川哲人、MBA、技術士
株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表、PMstyleプロデューサー
15年以上に渡り、技術経営のコンサルタントとして活躍。プロジェクトマネジメントを中心にした幅広いコンサルティングを得意とし、多くの、新規事業開発、研究開発、商品開発、システムインテグレーションなどのプロジェクトを成功に導く。
1万人以上が購読するプロジェクトマネジャー向けのメールマガジン「プロジェクトマネジャー養成マガジン」や「プロジェクト&イノベーション(無料」、書籍出版、雑誌記事などで積極的に情報発信をし、プロジェクトマネジメント業界にも強い影響を与え続けている。
メルマガ紹介
本連載は終了していますが、コンセプチュアル・マネジメント購読にて、最新の関連記事を読むことができます。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

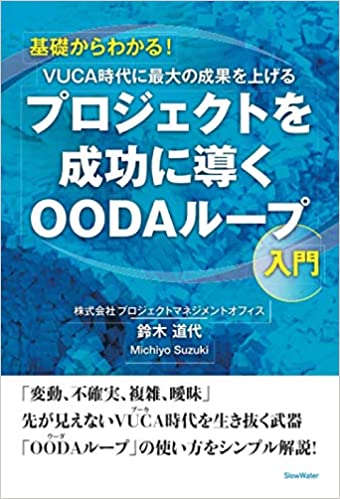
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/02/25,27☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/2/19☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/2/25☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/16☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/2/18☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/2/18,20☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/2/20☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/2/21☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索