競争に勝つためには次から次に連続的にイノベーションを起こしていく必要があり、イノベーションを俊敏にするために、プログラムマネジメントが必要
第74話:継続的イノベーションの時代のマネジメント(2013/11/20)
プロジェクトマネジメントオフィス 好川 哲人
◆イノベーションは意思を以って起こす
イノベーションは自然に起こるものではありませんし、誰か、優秀な社員が起こしてくれるものでもありません。イノベーションは意志を以って起こしていくものです。今回のPMスタイル考はイノベーションの話をしたいと思います。
今、イノベーションが注目されているのには戦略的な理由があります。10年前なら技術イノベーションを求めて研究開発を行い、うまく行けばその成果を使った事業戦略を立てて5〜10年単位で事業展開ができていました。今でもイノベーションにはこのイメージが残っていますが、戦略を組み立てる「ネタ」になるものでした。
◆戦略=イノベーション
ところが今はそのような状況ではありません。ひとつのイノベーションによる優位性がそんなに長続きせず、競争に勝つためには次から次に連続的にイノベーションを起こしていく必要が生じています。言い換えれば、戦略=イノベーション
という図式になってきました。この時代を象徴するのがアップルです。iPhoneというとてつもないイノベーションを実現したにも関わらず、毎年、新製品が発表される度に今年はどんなイノベーションがあるのかとユーザーから期待されています。そして、その期待に答えれなければ対価に見合わないと判断したユーザーは似て安い製品に移っていきます。
情報システムのような受注製品でも同じようなことが起こっています。ITのベンダーはこの10年、ソリューションということを盛んに訴えてきました。ソリューションビジネスとは顧客がビジネスやサービスについて抱えている問題や不便を解消することで、ITベンダーはそのために提供される情報システムを提供してきたわけです。
顧客のビジネスが5年、10年続いていた時代には、ソリューションは情報システムの更新に併せて提供すれば十分でしたが、上にのべたようにイノベーションが戦略として求められるようになるとソリューションもそのサイクルに併せて提供しなくてはなりません。
つまり、顧客の狙うイノベーションに併せてソリューションを提供しなくては顧客は満足せず、ここでは、
ソリューション=イノベーション
という図式ができつつあります。今後、ITベンダーが生き延びていく条件の一つにイノベーションを起こすソリューションを継続的に提供できることが間違いなく入ってくると思われます。
◆イノベーションマネジメントとプログラムマネジメント
さて、このようにイノベーションを継続的に起こしていくにはどうすればよいのでしょうか。冒頭にも述べましたように、成り行き任せではできないことは明らかです。そこでマネジメントが必要になってきます。
イノベーションを起こすには2つのマネジメントが必要です。一つはイノベーションを効果的に起こす組織的活動を実現するマネジメントです。これは「イノベーションマネジメント」と呼ばれます。具体的には戦略実現に必要なイノベーションのテーマを見つけ、資源配分を決め、イノベーションの成果をうまくビジネスに取り込んでいく戦略マネジメントです。
もう一つはイノベーション活動そのもののマネジメントが必要になります。イノベーションは通常の業務と異なり、目標が決まっても確実にその目標を達成できるという保証はありませんし、目標そのものが変わってしまう場合もあります。試行錯誤が不可欠です。
一方で、連続的にイノベーションを起こすにはリードタイムが問題になってきますので、できるだけ効率的に試行錯誤をしていく必要があります。そのためのマネジメントとしては、プログラムマネジメントが効果的です。
◆イノベーションを俊敏にするプログラムマネジメント
プログラムマネジメントの中でポイントになるのは、プログラムのデザインです。プロジェクトであれば目的、目標、前提、制約、体制
を決めれば事足りますが、プログラムの場合はもう少し複雑になります。PMstyleの場合、プログラムのデザインの要素を以下の9つとしています。
(1)ミッション
(2)ゴール
(3)製品・サービス
(4)収益
(5)アークテクチャー
(6)プログラムシナリオ
(7)リソース
(8)投資
(9)ベネフィット
(1)のミッションは、戦略実行のためにプログラムが実現すべき事項で、プログラムが生み出すべきの総体ということになります。
(2)のゴールは、ミッションを実現するためには何をゴールにすればよいかを明確にします。
(3)の製品・サービスはミッション実現のために開発する製品・サービスなどの成果物を明確にします。
(4)の収益はプログラムで得られる収益です。プログラムはその性格上、ミッションを達成し、ベネフィットを実現すると同時に、財務的な収益も求められることが普通です。ただし、組織変革プロジェクトのように組織内部のプロジェクトの場合には収益は必要ないケースもあります。
(5)のアーキテクチャーはプログラムのベネフィットを生み出すための個々の活動の定義です。具体的にはプログラムとして実施するプロジェクトの定義になります。
(6)のプログラムシナリオはアークテクチャーでプログラムのベネフィットが実現できる可能性を示すものです。複数のシナリオを可能性として示すのが普通です。
(7)のリソースはプログラムの実行に必要なリソース、(8)の投資はプログラムへの投資です。
(9)のベネフィットはプログラムがもたらすベネフィットですが、一般的には戦略にどのように貢献できるかだと考えていいでしょう。
◆プログラムキャンパス
この9つの要素をバランスを取りながら決めることによってプログラムをデザインします。プログラムのデザインにおいては、バランスを可視化できるようにプログラムキャンパスというツールを使います。プログラムキャンパスは(1)〜(4)を価値のキャンパス、(5)〜(8)を最適化のキャンパスとして、両者からベネフィットが最大になるようにデザインするツールです。具体的には価値のキャンパスで価値を最大化し、最適化のキャンパスでリソースや投資を調整します。
プログラムキャンバスを使って構造的に考えることによって、効果的なプログラムの設計が可能になります。
◆関連セミナー
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆コンセプチュアルな組織を創るマネジメント ◆(7PDU's)
日時・場所:【Zoom】2026年 05月 12日(火)9:30-17:30(9:20入室可)
※Zoomによるオンライン開催です
※ハーフセミナーは、事前学習3時間あります
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木道代(プロジェクトマネジメントオフィス、PMP、PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/conceptual_management.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「コンセプチュアルスキルとは(前半)」「コンセプチュアルスキルで行動が変わる」
「イノベーションを生み出す力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.コンセプチュアルではない組織の問題点
・個人レベルの問題点
・チームレベルの問題点
・組織レベルの問題点
2.コンセプチュアルなマネジメントのポイント
2.1 質問型の組織を創る
2.2 コンセプチュアルな組織活動のプラニング
2.3 ステークホルダーへのコンセプチュアルな対応
2.4 コンセプチュアルな人材育成
2.5 コンセプチュアルな組織文化の構築
3.コンセプチュアルなマネジメントの目標
4.コンセプチュアルマネジメントでコンセプチュアルな組織を創る仕組みワークショップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者紹介
好川哲人、MBA、技術士
株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表、PMstyleプロデューサー
15年以上に渡り、技術経営のコンサルタントとして活躍。プロジェクトマネジメントを中心にした幅広いコンサルティングを得意とし、多くの、新規事業開発、研究開発、商品開発、システムインテグレーションなどのプロジェクトを成功に導く。
1万人以上が購読するプロジェクトマネジャー向けのメールマガジン「PM養成マガジン(無料版)」、「PM養成マガジンプロフェッショナル(有料版)」や「コンセプチュアル・マネジメント(無料」、書籍出版、雑誌記事などで積極的に情報発信をし、プロジェクトマネジメント業界にも強い影響を与え続けている。
メルマガ紹介
本連載は、PMstyleメールマガジン購読にて、最新記事を読むことができます。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

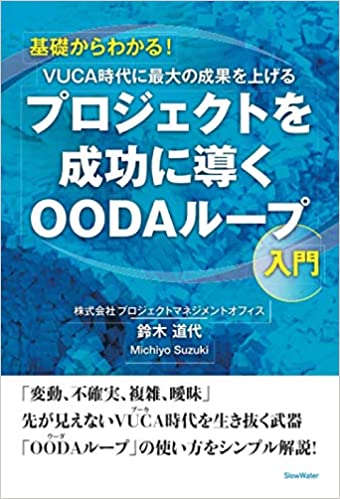
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/06/17,19☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/6/11☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/4/1☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/12☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/18☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/27,29☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/5/28☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索