イノベーションを起こそうと取り組んでも、失敗を恐れているから改善にとどまり、改革と名がつくことに手を伸ばそうとはしないが、失敗コストが小さくなっている今、管理から、マネジメントに移行しよう
第167話:失敗に対する認識を改める〜機会コストが失敗コストを上回る時代(2020/03/25)
プロジェクトマネジメントオフィス 好川 哲人
◆はじめに
PMstyle+も本号で300号になるので、PMスタイル考にもなにか少し大きな話を書いてみようと思ってたどりついたのが、失敗の話である。アジャイルプロジェクトマネジメントが注目されだしたあたりから、失敗に対する評価を変えようという話をよく聞くようになってきた。実際に、そのような取り組みをして、ずいぶん失敗に寛容だなあと感じる組織もある。先日、ある知人から聞いた話だが、そのような取り組みの成果が出ていないという相談を受けた。曰く「失敗を許容するようなプロジェクト制度と評価制度を創ったのに、失敗が増えないし、イノベーションも生まれない」。
結構、同じような話を聞く。
なぜだろうかと考えたときに、失敗に寛大になるのは精神論で、そのようになる根拠(必然)がないと考えているリーダーが多いのだ。これは、失敗に対する「望ましくないこと」だという認識が変わっていないためだと思われる。
実はこの話は精神論ではない。そういう世の中になる節目にあるし、それを理解し、取り込んでいくことがVUCA時代に対応する必須条件でもある。
今回のPMスタイル考はこの話題を取り上げてみたい。
◆イノベーションの生まれない原因
IMF(国際通貨基金)が、このままでは日本の人口が大幅に減少し、40年後にはGDP(国内総生産)が25%減少するという発表をした。人口が減少することとGDPが減少することの関連性は避けがたいというのが一般的な認識であるが、ただ、日本の生産性の現状を考えるとある程度は人口減の影響を食い止めることができるのではないかとも思う。そのために不可欠なのが、イノベーションにより高価値のサービスや製品を生み出していくことであるが、その妨げになっているのが失敗に対する意識である。これもよく言われることだが、イノベーションを起こそうと取り組んでも、失敗を恐れているから改善にとどまり、改革と名がつくことに手を伸ばそうとはしない。挙句の果てが、分類上は改善も立派なイノベーションだと言いだす人も出てくる始末だ。
今回のPMスタイル考は改めてこの問題について考えてみたい。
◆失敗コストを機会コストが上回ってきた
ライプニッツ代表の山口周さんが、エイミー・ウィテカー氏の「アートシンキング〜未知の領域が生まれるビジネス思考」(ハーパーコリンズ・ジャパン、2020)の前書きで以下のような興味深い指摘をしている。「ビジネスとアートの違いは失敗コストの大きさだった。アートにおける失敗はコストが小さいが、ビジネスにおいては失敗のコストが大きかった。なぜならビジネスにおいては失敗するとその後の精算に膨大なコストがかかっていた。工場を建て、人を雇っているので固定費の精算が膨大になるからだ。
しかし、今の時代は極めて柔軟に人材・テクノロジー・資金・技術を外部から調達するためのインフラが整いつつあるため、ビジネスにおいても失敗コストが小さくなってきている。」
というものだ。
その代表がアマゾンである。アマゾンは1997年のNASDAQ上場以来、二十数年の間に約70の新規事業に進出し、そのうち三分の一が失敗して早期に撤退している。これは、失敗のコストが低くなっているからだと指摘している。
アマゾンの場合、事業リソースを内部化せずに、適時・適宜に外部から調達している。このため、撤退しても大きなコストがかからず、そのようなやり方を可能にしている。
このように失敗コストが小さくなることによって、むしろ「機会コスト」の方が大きくなるようになっている。
「機会コスト」はあまり耳にしない用語かもしれないが、複数ある選択肢の内、ある期間の中で最大利益を生む選択肢とそれ以外の選択肢との利益の差を指している。
簡単な例で説明しよう。
ある組織が実施しているA事業では100万円儲かっていたが、B事業なら150万円儲かっただろうと推測されるなら、差である50万円が機会コストになる。以前であれば、仮に事業Bの機会コストが50万円あることが分かっても、事業Aの撤退(失敗コスト)に70万円かかるので事業Aを継続する方が良かった。
余談になるが、この例だと、10万円の赤字が出ても継続する方が良いし、新しい事業にはリスクがあるため、赤字になっても撤退の意思決定ができないことが少なくなかった。
ところが撤退に30万円しかかからないと話が変わってくる。機会コストの50万円の方が大きくなる。こうなると儲けの小さいA事業から撤退して、より儲かるB事業に進出した方が儲けが大きくなる。これがアマゾンが多くの新規事業を手掛けながら、三分の一の事業から撤退している理由である。これはグーグルやフェイスブックにも共通している特徴だ。
◆失敗は本当に許容されているのか
かつて、日本は一度、企業を潰す(失敗する)と、二度とチャンスが与えられないとされていた。そのため、起業するのは準備が大変で、万全の準備をしてから事業を始めていた。一方で、一旦、事業を始めるとそう簡単には撤退しない(できない)のが普通だった。しかし、今は起業しても比較的容易に撤退でき、また、次のチャンスにかけることできるようになったのは、失敗コストが低減されているからである。ソフトうエア事業やサービス業はもちろんのこと、ハードウエアが不可欠な製造業においてもさまざまなインフラが整ってきて、同じような傾向にある。
また、企業内ベンチャーにおいてもこの傾向がみられる。企業内ベンチャーとして期間を決めてとりあえずやってみて、事業計画通りにいかなければ撤退するというやり方をしている例は珍しくない。企業内ベンチャーの場合、親企業の人やモノを活用し、失敗したときに迅速に撤退することを容易にしているケースもみられる。
しかし、本当に失敗が許容されているかというと微妙なところがある。ここに存在しているのが、顧客側の不寛容さである。日本企業は社員のミスやクオリティの低下を許容しないという傾向があるが、その源泉になっているのが顧客の不寛容さである。顧客は当然のごとく、ミスがなく、クオリティの高いサービスや製品を要求する。これに対応しようとすれば、それを提供する人やシステムのクオリティの高さを求め続けるしかない。
失敗を許すと言いながら、許されていない背景には、「会社としては仕方ないと思うのだが、顧客が許さない/市場が許さない」という構図がある。結局のところ、会社としても失敗を許さないということになるのだ。
◆不寛容さが改善にとどめている
そして、詰まるところ、このようなやり方が改革を躊躇させ、改善にとどめている。これは、いろいろな企業が発表している製品やサービスを見ていると一目瞭然である。このようなやり方をしている大きな問題は、山口さんが指摘しているように「機会」を逃すことである。
製品やサービスを改善しても、生まれてくるのは微妙な市場の拡大である。すると、需要は買い替えになる。買い替え需要が主体になると、価格は徐々に下げざるを得ない。
一方で機能は向上し、物価も上がってくるので、コスト(原価)は上がってきて、利益は徐々に少なくなってくる。バブルの崩壊とともにこういうビジネススタイルが主流になっている。このままで進のは限界だと言われながら、製造業においては製造拠点の海外移動による人件費の低減、設計の工夫による製品原価の低減、生産ラインの自動化による製造コストの低減などに取り組み、しぶとく生き残っている。サービス業においても、人件費の低減、仕入れ方法や物流方法の工夫による原価の低減などに取り組み、なんとか生き延びている。
しかし、今のやり方を今後何十年も維持できるとは思えない。やり方を変え、機会を逃さないためには、根本的に失敗は望ましくないことだという「認識」を変える必要がある。
◆プロジェクトに見られる傾向
さて、では高付加価値を求めた活動であるプロジェクトではこの問題はどうなっているのだろう。本来、プロジェクトは時限の活動であるため、リソースを外部から調達をすることが前提になっている。にも関わらず、現実には固定化していることが少なくない。その典型が人材であろう。人材は外部化されているが、それが固定的なのだ。人材不足を理由に抱え込むことに苦心している。特に、優秀な人材に対してはその傾向が強い。
これでは、単にコストを下げるために外部化しているだけで、本質的には内部化しているのと変わらない。
プロジェクト用の機器や施設なども同じような傾向が伺えるが、この最も本質的な理由はやはり、失敗をしたくないという意識だろう。特に、この20年くらいの間にプロジェクト制度が確立してきて、プロジェクトの事前評価が確実に行われるようになってきた。ところが、プロジェクト評価を現場主体で行っているため、リスクが取れない。
新製品の開発にしろ、新サービスの開発にしろ、個別顧客対応にしろ、付加価値を高くしようとするとリスクを取ることになる。これはイノベーションの本質である。ところが現場だけでプロジェクト評価をするとリスクを取ることを嫌う。人的リソースも内部化に近い。その中で新しいものが求められるので、必然的になにがしかの改善にならざるを得ない。
例えば、システム開発の事業をやっているS社で、これまでに例がないシステムを作るという引き合いがあり、高い収益を上げるチャンスがあった。営業は受注したいと考えていたが、結局、提案金額の関係で現場だけで行った提案評価会議で、過去に実績がないことと、技術の経験者がいないことを理由に入札しなかった。競合も同じような事情だと思われたが、競合の一社が。S社より高い金額で受注し、見事に開発に成功した。余談だが、あとで知ったS社の役員は受注すればその成果を他の案件に入れ込むことができるので、赤字でも提案していたのにとぼやいていた。
◆改めて管理からマネジメントへ
これはプロジェクトマネジメントの考え方と違う。もっと言えば、プロジェクト管理であって、プロジェクトマネジメントではない。こういう場合に、その技術や経験を持っているリソースを外部から調達してきて、進めていくのがプロジェクトマネジメントである。失敗する可能性もあり、失敗すると納期に間に合わないというリスクもある。
そのようなリスクをマネジメントしながら、成果を上げるのがプロジェクトマネジメントである。リスクだけを強調し、安全な案件だけに取り組んでいくのであれば、機会コストが大きくなる。
結局、現実にはそんなに大きくない失敗コストにおびえて、失敗に対して非常に敏感になっており、それがどんどんエスカレートしている。この傾向は本来試行錯誤を目指しているアジャイルでも例外ではない。アジャイルの場合、それが有効性を阻害する本質的な原因になっている。
皮肉なことにこの20年くらいプロジェクトマネジメントの強化によって、管理の傾向が強くなってきた。そろそろ、マネジメントに移行しよう!
◆関連セミナーのご案内
━【開催概要】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆コンセプチュアルな組織を創るマネジメント ◆(7PDU's)
日時・場所:【Zoom】2026年 05月 12日(火)9:30-17:30(9:20入室可)
※Zoomによるオンライン開催です
※ハーフセミナーは、事前学習3時間あります
※少人数、双方向にて、演習、ディスカッションを行います
講師:鈴木道代(プロジェクトマネジメントオフィス、PMP、PMS)
詳細・お申込 https://pmstyle.biz/smn/conceptual_management.htm
主催 プロジェクトマネジメントオフィス、PMAJ共催
※Youtube関連動画「コンセプチュアルスキルとは(前半)」「コンセプチュアルスキルで行動が変わる」
「イノベーションを生み出す力」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【カリキュラム】
1.コンセプチュアルではない組織の問題点
・個人レベルの問題点
・チームレベルの問題点
・組織レベルの問題点
2.コンセプチュアルなマネジメントのポイント
2.1 質問型の組織を創る
2.2 コンセプチュアルな組織活動のプラニング
2.3 ステークホルダーへのコンセプチュアルな対応
2.4 コンセプチュアルな人材育成
2.5 コンセプチュアルな組織文化の構築
3.コンセプチュアルなマネジメントの目標
4.コンセプチュアルマネジメントでコンセプチュアルな組織を創る仕組みワークショップ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
著者紹介
好川哲人、MBA、技術士
株式会社プロジェクトマネジメントオフィス代表、PMstyleプロデューサー
15年以上に渡り、技術経営のコンサルタントとして活躍。プロジェクトマネジメントを中心にした幅広いコンサルティングを得意とし、多くの、新規事業開発、研究開発、商品開発、システムインテグレーションなどのプロジェクトを成功に導く。
1万人以上が購読するプロジェクトマネジャー向けのメールマガジン「PM養成マガジン(無料版)」、「PM養成マガジンプロフェッショナル(有料版)」や「コンセプチュアル・マネジメント(無料」、書籍出版、雑誌記事などで積極的に情報発信をし、プロジェクトマネジメント業界にも強い影響を与え続けている。
メルマガ紹介
本連載は、PMstyleメールマガジン購読にて、最新記事を読むことができます。
プレミアム会員は、年間、17.5時間または35時間または70時間受講できます。また、希望日時、マンツーマンでも、受講できます
Youtube始めました。チャンネル登録お願いします。PMstylebiz

書籍&チケットプレゼントはこちらから
お薦めする書籍

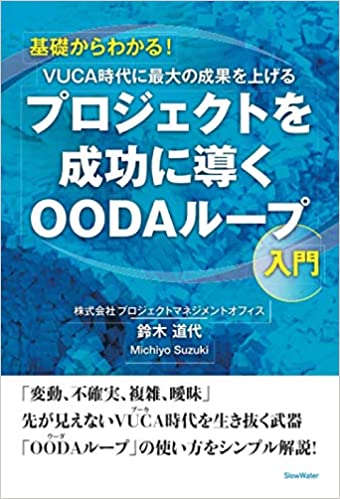
メルマガ購読
ブログ
公開セミナー(カテゴリー別)
日付順 カレンダー
お客様の声(掲載をご許可いただいた受講者の方のアンケート結果)
- すべてのセミナーが企業研修(5名以上から)に対応できます。夜間開催、オンライン開催可能ですお問合せはこちらから
- ☆ 公開セミナー おすすめ ★
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoom】PM養成講座(全5回)ビデオ+ 月曜曜午後2.5時間
- 26/4/13,4/27,5/11,5/25,6/8☆【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)ビデオ+月曜夜間2.5時間
- 26/4/16☆【Zoom】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル★開催決定★
- 26/5/13☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- 26/06/17,19☆【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門〜本質を見極め、行動するスキル
- ☆ 新規講座 ☆
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/5/8☆【Zoom】イノベーション力を身につける
- 26/6/11☆【Zoom】問いから始まるイノベーション
- 26/6/5☆【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント
- 26/4/21☆【Zoom】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/4/1☆【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- 26/05/13,15☆【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント〜良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる
- − 2025年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/2/28☆【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/2☆【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る
- 26/3/4☆【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- 26/3/4,6☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/3/6☆【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る
- 26/3/7☆【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/3/9☆【Zoom】ベンダーマネジメント
- 26/3/11☆【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/3/11,13☆【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/3/14☆【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/3/16☆【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上
- 26/3/18☆【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/3/25,27☆【Zoomナイト 】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方★開催決定★
- 26/3/27☆【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/3/28☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- − 2026年度 −
個人受講割引(半額)あり☆ - 26/4/7☆【Zoom】プロジェクト知識マネジメント〜質の高い振返りでプロジェクトを変える
- 26/4/8☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/4/8,10☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/4/9☆【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営
- 26/4/14☆【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方
- 26/4/15☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/4/15,17☆【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/4/20☆【Zoom】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- 26/4/22☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/4/23☆【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/4/28☆【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際
- 26/4/22,24☆【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/12☆【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
- 26/5/14☆【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決
- 26/5/18☆【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント
- 26/5/19☆【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践
- 26/5/20☆【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用〜VUCA時代の思考法
- 26/5/20,22☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座
- 26/5/21☆【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント
- 26/5/27,29☆【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践
- 26/5/28☆【Zoom】プロジェクトマネジント手法の確立と標準化
- 26/5/29☆【Zoom】リカバリーマネジメント
- 26/6/10,12☆【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践
- 26/6/24☆【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門〜システム思考で考える
- −日程未定−
- ☆【Zoomハーフ】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomナイト】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomナイト】コンセプチュアルなチームを創る
- ☆【Zoomハーフ】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント
PMコンピテンシーとは
サイト内検索